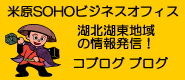『自助論』
 第10回
第10回皆さん、こんにちは。
税理士・行政書士・ラジオコメンテーターの小川宗彦です。
「経営に役立つビジネス書10選」について、私が選び抜いた厳選ビジネス書を全10回シリーズでお届け致します。
順風満帆のときも逆境のときもあなたを勇気づけてくれる「座右の書」が必ずあります。
読み継がれている良書と出会うことで、自ら考え、自ら行動するビジネスパーソンになって頂きたいと思います。
それでは、早速参りましょう!
第10回 「経営に役立つビジネス書10選」
~『自助論』~12月9日号
『自助論』‐人生を最高に生きぬく知恵‐
サミュエル・スマイルズ著
2002年発行 竹内 均訳 三笠書房
今回、ご紹介する「経営に役立つビジネス書」は、原書は1858年に書かれ、日本では1871年に『西国立志編』と題して邦訳され、福沢諭吉の『学問のすすめ』と並んで明治期の青年たちに広く読まれたという、サミュエル・スマイルズの世界的名著、『自助論』です。
「天は自ら助くる者を助く」。
私がこの格言に出会い、その意味するところを理解しようとしたあの日、とてつもない衝動が全身を走ったことが今でも忘れられません。
自助努力の精神・・・。
自助とは、勤勉に働いて、他人に頼るのではなく、自分で自分の運命を切り拓くことです。
本書は、コツコツ努力することは決してカッコ悪いことではなく、日々の少しずつの改善の積み重ねが人生を決めていくという真理を多くの人物の例をあげて、豊富なエピソードを元に普遍的なことが書かれています。
たとえば、「人生に暇な時間はない」「常識に明るく、辛抱強い人間になること」「逆境の中でこそ若芽は強く伸びる」など、いわば当たり前の内容が当たり前に書かれているのですが、私は何か困難な出来事に直面したときこの本を改めて読むと、自分が立ち返る原点に戻ることができます。
サミュエル・スマイルズいわく、「ビジネスでは、頭を使い、情熱をもって実践していくことが成功の秘訣だ。」と述べているとおり、「自助」を突き詰めれば、自分の目指すべき姿、それは、「自己実現」ともいうべき、「成果を上げる人」になることです。
つまり、「成果を上げる人になる=自己実現」ということは、自己修練で習得できるということなのです。
これは、人から教わるものでもなく、一部の人だけのものでもなく、一人ひとりの「自助」により手にいれることのできる産物なのです。
どんなに辛く悲しいときも本書を心の支えにして頂ければと思います。
何より、自己鍛錬の書として、かけがいのない人生を共にするそんな一冊です。
最後に、前作に引き続き、今回も編集を担当して下さった滋賀県産業支援プラザの船越英之さん、同じく日ごろお世話になっている滋賀県産業支援プラザの山本照美さん、谷口直樹さん、そして中川伸幸さん、ありがとうございます。
この方々の存在なくして、この連載コラムは世に出ることはなかったでしょう。
同じ時代を生きる起業家の皆さんと、「ビジネス書」というテーマを通じてつながることができたことをとても嬉しく思っています。
本当にありがとうございます。
希望に満ちた起業家の皆さんとは、現実のビジネスシーンでお会いできることを心より楽しみにしています。
これからも「ビジネス書」を読み続け、ビジネスに活かして行きましょうね!
それでは、また!
『人を動かす』
 第9回
第9回皆さん、こんにちは。
税理士・行政書士・ラジオコメンテーターの小川宗彦です。
「経営に役立つビジネス書10選」について、私が選び抜いた厳選ビジネス書を全10回シリーズでお届け致します。
順風満帆のときも逆境のときもあなたを勇気づけてくれる「座右の書」が必ずあります。
読み継がれている良書と出会うことで、自ら考え、自ら行動するビジネスパーソンになって頂きたいと思います。
それでは、早速参りましょう!
第9回 「経営に役立つビジネス書10選」
~『人を動かす』~12月2日号
『人を動かす』‐HOW TO WIN FRIENDS AND INFLUENCE PEOPLE‐
デール・カーネギー著
1936年刊 創元社 1999年発行 山口博訳
今回、ご紹介する「経営に役立つビジネス書」は、ビジネスパーソンとして身につけるべき人間関係の原則を著者の15年にわたる教育経験から具体例を豊富に交えて解説し、あらゆる自己啓発本の原点となったデール・カーネギーの不朽の名著、『人を動かす』です。
著者のデール・カーネギーは、農家の出身に生まれ、ミズーリ州立学芸大学卒業後、新聞記者、俳優、セールスパーソンなど様々な職種を経て、ニューヨークYMCAで「ビジネスマンのための話し方講座」を始めたところ、「話し方」という当初の領域を超えて対人関係で成功するシンプルな法則を提示し、自分自身や他の人の経験、歴史上の人物を例に取って、人間関係全般に言及した講座が人気を博することになりました。
やがて、この成功を契機にデール・カーネギー本人の考えを広げるために、D・カーネギー研究所設立し、人間関係の先駆者として、今で言うところのカリスマ・人材コンサルタントに上り詰めたのです。ちなみに、実業家のアンドリュー・カーネギーとは血縁関係にありません。
さて、本書の第一章では、デール・カーネギーが単刀直入に、「人を動かす三原則」として、1.盗人にも五分の理を認める、2.重要感を持たせる、3.人の立場に身を置く、の三つを挙げています。
たとえば、原則一「盗人にも五分の理を認める」とは、他人を批判、非難することは利益がないからやめようという原則です。
デール・カーネギー曰く、「人間はたとえ自分がどんなにまちがっていても決して自分が悪いとは思いたがらないものだ。」だから、「他人のあら探しは、なんの役にも立たない。相手は、すぐさま防御体制をしいて、なんとか自分を正当化しようとするだろう。それに、自尊心を傷つけられた相手は、結局、反抗心をおこすことになり、まことに危険である。」と述べています。
次の原則二「重要感を持たせる」では、相手の重要感を高めようという原則です。
つまり、「人間は例外なく他人から評価を受けたいと強く望んでいるのだ。この事実を、決して忘れてはならない。」と述べられ、深い思いやりから出る感謝の言葉をふりまきながら日々を過ごすこと、これが、友をつくり、人を動かす秘訣であるというのです。
そして、この原則を実行するために、デール・カーネギーは古い名言を鏡に貼って自分に言い聞かせたそうです。何とも深すぎるセンテンスです。
「この道は一度しか通らない道。だから、役に立つこと、人のためになることは今すぐやろう―先へ延ばしたり忘れたりしないように。この道は二度と通らない道だから。」
最後に、原則三「人の立場に身を置く」では、常に相手の立場に立ってものごとを考えるという原則です。
「人を動かす唯一の方法は、その人の好むものを問題にし、それを手に入れる方法を教えてやることだ。これを忘れては、人を動かすことはおぼつかない。・・・」と述べられ、極めてシンプルな原則です。
以上のように、本書では「人を動かす三原則」のほかにも他の章で、「人に好かれる六原則」、「人を説得する十二原則」、「人を変える九原則」、「幸福な家庭をつくる七原則」が記され、どの章も先人たちの教訓がエピソードとともに紹介されています。
いずれにしても、デール・カーネギーの一番大切な教えは、次のセンテンスに集約されています。
それは・・・。
「人を動かす秘訣は、この世に、ただ一つしかない。この事実に気づいている人は、はなはだ少ないように思われる。しかし、人を動かす秘訣は、間違いなく、一つしかないのである。すなわち、みずから動きたくなる気持を起こさせること‐これが秘訣だ。」
誰もが行動したくなるような気持ちにさせるのが、リーダーの本当の役割なのかも知れませんね!
このように本書は随所に賢者の名言が満載です。
本書を片時も離さず、カバンの中に携行し、すきま時間で使って心ゆくまで「人間の本質」を楽しんで下さい。
きっと何かが変わってくると思います。
次回、12月9日号は全10回の最終回です。
それでは、また!
『マネジメント‐課題、責任、実践(上・中・下)‐』
 第8回
第8回皆さん、こんにちは。
税理士・行政書士・ラジオコメンテーターの小川宗彦です。
「経営に役立つビジネス書10選」について、私が選び抜いた厳選ビジネス書を全10回シリーズでお届け致します。
順風満帆のときも逆境のときもあなたを勇気づけてくれる「座右の書」が必ずあります。
読み継がれている良書と出会うことで、自ら考え、自ら行動するビジネスパーソンになって頂きたいと思います。
それでは、早速参りましょう!
第8回 「経営に役立つビジネス書10選」
~『マネジメント‐課題、責任、実践(上・中・下)‐』~11月25日号
『マネジメント‐課題、責任、実践(上・中・下)‐』
ピーター・F・ドラッカー著
2008年刊 ダイヤモンド社
今回、ご紹介する「経営に役立つビジネス書」は、20世紀から21世紀にかけて経済界に最も影響力のあった経営思想家であり、世界最高の経営コンサルタントと称される、ピーター・F・ドラッカー著の『マネジメント‐課題、責任、実践(上・中・下)‐』です。
マネジメントの父・・・。
その名は言わずと知れた、ピーター・F・ドラッカー。
今では、当たり前のように使われている目標管理、自己分析、時間管理、自己実現、イノベーションといった概念を実際にビジネスの現場で活用できるような形にして世に送り出したのは、何を隠そうこのドラッカーなのです。
さて、本書の『マネジメント』は、つまるところ、「組織」が着実に成果を挙げるためのものの見方、考え方、そして行動のエッセンスを1400ページにわたり、詳しく説いています。
現代社会では、あらゆる仕事が組織を通じ、組織において行われるようになってきていますが、果たしてそこで働く人が生き生きとし、いい仕事をするような組織になっているだろうかという、ドラッカーの問題意識から本書は始まります。
つまり、「組織」が機能し、成果を挙げるようにすることが、マネジメントの役割であり、ドラッカーはこのマネジメントを次のように定義しています。
「マネジメントには、自らの組織をして社会に貢献させるうえで三つの役割がある。それら三つの役割は、異質ではあるが同じように重要である。
(1)自らの組織に特有の目的とミッションを果たす。
(2)仕事を生産的なものとし、働く人たちに成果をあげさせる。
(3)自らが社会に与えるインパクトを処理するとともに、社会的な貢献を行う。」
ドラッカーのいうところのマネジメントの目的は、自らの組織を社会に貢献させることであり、組織が存在するのは、組織自体のためではなく、自らの組織機能を果たすことによって、社会、コミュニティ、個人のニーズを満たすために組織は存在すると考えているのです。
「組織」の運営のされ方いかんで、大きく言えば、世の中は、良くもなり悪くもなるというのです。
そして、この「マネジメント」には欠かせない大事な要素があります。
それは、「真摯さ」です。
ドラッカーの言葉を引用すれば、「事実、うまくいっている組織には、必ず一人は、手をとって助けもせず、人づきあいもよくない者がいる。この種の者は、気難しいくせにしばしば人を育てる。好かれている者よりも尊敬を集める。一流の仕事を要求し、自分にも要求する。基準を高く定め、それを守ることを期待する。何が正しいかだけを考え、誰が正しいかを考えない。~中略~マネジメントにできなければならないことは学ぶことができる。しかし、学ぶことのできない資質、後天的に獲得することのできない資質、初めから身につけていなければならない資質が一つだけある。才能ではない。真摯さである。」
なるほど、この「真摯さ」こそ、マネジメント唯一絶対の条件であり、真のマネージャーたる資質なのかも知れませんね。
ドラッカーの世界において、すべての鍵は、一人ひとりの人間です。「人間愛の追求」と言っていいかも知れません。
ビジネスで困難に直面し、組織で悩みを抱えている多くの人が、ドラッカーに救われます。
きっと、本書こそ、読者の皆さんの真摯な悩みに答えてくれる至高の一冊となるでしょう!
それでは、また!
『ザ・コピーライティング‐心の琴線にふれる言葉の法則‐』
 第7回
第7回皆さん、こんにちは。
税理士・行政書士・ラジオコメンテーターの小川宗彦です。
「経営に役立つビジネス書10選」について、私が選び抜いた厳選ビジネス書を全10回シリーズでお届け致します。
順風満帆のときも逆境のときもあなたを勇気づけてくれる「座右の書」が必ずあります。
読み継がれている良書と出会うことで、自ら考え、自ら行動するビジネスパーソンになって頂きたいと思います。
それでは、早速参りましょう!
第7回 「経営に役立つビジネス書10選」
~『ザ・コピーライティング‐心の琴線にふれる言葉の法則‐』~11月18日号
『ザ・コピーライティング‐心の琴線にふれる言葉の法則‐』
ジョン・ケープルズ著、神田昌典監訳、齊藤慎子+依田卓巳訳
2008年刊 ダイヤモンド社
今回、ご紹介する「経営に役立つビジネス書」は、原書の初版は1932年。それ以来、「現代広告の父」デビッド・オグルヴィも学び、多くの広告人にバイブル本として読み継がれてきた、ジョン・ケープルズ著の『ザ・コピーライティング‐心の琴線にふれる言葉の法則‐』です。
ジョン・ケープルズは、アメリカの広告業界で49年もの間、コピーライターとして活躍し続け、その間、常に広告のテストを繰り返し、効果を検証する「科学的広告」を目指し続けた伝説のコピーライターです。
広告には、大きく2つの分類に分けることができますが、そのひとつは「商品やサービスのイメージを上げるための広告」。もうひとつは「商品やサービスを知ってもらい、購入につなげるための広告」です。
前者を「イメージ広告」といい、後者は「レスポンス広告」と言います。
本書で述べられているのは、まさにこの「レスポンス広告」手法で、ジョン・ケープルズ自身が、半世紀のキャリアを通じて検証したのは、広告の売上に対する反応を顧客からの問合せや資料請求数等の具体的数値で把握し、効果を挙げるコピーライティング、つまり「科学的広告」の原理原則と、「言葉が富を産む」成功例と失敗例を交えた実践的コピーです。
なかでも興味深いのは、インターネットが普及した昨今でも、この本に書かれている内容は、より実践的・効果的に使えるからです。
たとえば、この本の中でジョン・ケープルズが、「ある広告が、他の広告の19.5倍の売上をもたらしたケースを知っている」と述べていますが、その方法として具体的には次のようなことを紹介しています。
①最大限の費用対効果へのカギは、広告のあらゆる要素を絶えずテストすることにある。
②どう言うかより、何を言うかの方が重要。
③ほとんどの広告では、見出しが1番重要。
④1番効果的な見出しは、相手の「得になる」とアピールするか、「新情報」を伝えるもの。
⑤中身のない短い見出しより、何かをきちんと伝えている長い見出し方が効果的。
⑥一般的な内容より、具体的な内容の方が信用される。
⑦短いコピーより、長いコピーの方が説得力がある。
このように、コピーライティングの真髄とも言える本書の要点は、次の2点にあります。
まず、「広告の法則を科学的に説明する」とあり、どんな広告で商品が1番よく売れるか、どんな見出しが1番注目されるか、どの媒体が最適か、どんなビジュアルとレイアウトが1番効果的かを教えてくれています。
そして、「広告をテストする方法を説明する」では、最も効果的な、見出し・訴求ポイント・ビジュアル・コピー・媒体が何であるかを自分で判断できるようになるということを学ぶことができます。
しかしながら、広告を打つということは、まさに諸刃の剣です。
広告の言葉が「顧客を動かし、富を産み続ける」反面、広告表現自体が敵を作ってしまったり、誰かを傷つけてしまったりする場合には、長期的にはうまくいかないのです。
それほど、広告の「言葉の力」というのは恐ろしいものです。
本書は、「言葉の力」を理解しようとするすべてのビジネスパーソンにとって必読の書です。
しっかり読んで「心の琴線にふれる言葉」をみつけたいですね!
それでは、また!
『競争の戦略』
 第6回
第6回皆さん、こんにちは。
税理士・行政書士・ラジオコメンテーターの小川宗彦です。
「経営に役立つビジネス書10選」について、私が選び抜いた厳選ビジネス書を全10回シリーズでお届け致します。
順風満帆のときも逆境のときもあなたを勇気づけてくれる「座右の書」が必ずあります。
読み継がれている良書と出会うことで、自ら考え、自ら行動するビジネスパーソンになって頂きたいと思います。
それでは、早速参りましょう!
第6回 「経営に役立つビジネス書10選」
~『競争の戦略』~11月11日号
『新訂 競争の戦略』
マイケル・E・ポーター著、土岐坤、中辻萬治、服部照夫訳
1995年刊 ダイヤモンド社
今回、ご紹介する「経営に役立つビジネス書」は、経営論の何たるかを知るための書であり、ビジネスを「戦略」の域に高めた経営戦略論の世界的権威、マイケル・E・ポーター著の代表的古典作、『競争の戦略』です。
「知っていないと話にならない!」なんて言われるくらい、本書は「競争」という概念の解説に始まり、企業が競争に勝つための戦略とその基本的なフレームワークの策定方法までを詳述している、経営書の基本中の基本です。
ところが、本書は邦訳本で462ページにも及ぶ大作で、ページ数が多いことも手伝って、従来から難解な書として扱われてきましたが、「『競争の戦略』を読まずして戦略を語る。」なんてことはできなくなっています。
なぜなら、マイケル・E・ポーターの「競争」のフレームワークが頭に入っていない状態でビジネスをするのはとても危険なことだからです。
たとえば、本書の副題にもあるように、「業界および競合を分析するための技法」として、「ファイブ・フォース」と「3つの戦略」が特に重要になります。
まず、自社の属する業界をファイブ・フォース(5つの競争要因)で競争環境を分析し、この結果に基づいて、自社の取るべきポジショニングを考察しようとするものです。
「競争」には、①競争業者、②新規参入業者、③買い手、④供給業者、⑤代替品の5つの競争要因があると定義されています。
よくある失敗例として、ビジネスを展開しようとするとき「競争業者」の中だけで経営戦略を立案してしまうケースで、実際には「競争業者」の動きだけを見ていては間違えてしまうからです。
実は、業界を取り巻くその他の競争環境の方がよほど重要だからです。
つまり、「新規参入業者」はどうか、「買い手」はどうか、「供給業者」はどうか、さらに「代替品」はどうかを考える必要があり、業界の競争要因を把握した上で、最も影響力の大きい競争要因の特定が戦略策定の決め手になると著者は述べています。
次に、上記のファイブ・フォースと並んで重要になるのが、3つの基本戦略です。これは、5つの競争要因から自社を守るための長期的な戦略で、①コストリーダーシップ(低コスト化)、②差別化戦略(業界の中でも特異な何かを創造する)、③集中戦略(特定のセグメントに資源を集中)が挙げられ、結局のところ、「基本戦略はこの3つしかない」と著者は指摘しています。
たとえば、業績不振であえいでいる多くの企業は、この3つの基本戦略のいずれも採用していないことや短期間で戦略を転換して一貫性がないと言われています。
逆に、「3つの基本戦略を同時に実行できる企業はほとんどない」と指摘し、選択した戦略によって、企業の行動は大きく変わるとも述べています。
その反面、リスクも背負っていることをお忘れなく・・・。
いずれにしても、企業は、明確に意図されているか否かにかかわらず、必ず「競争戦略」をもっています。そして、「競争の恐ろしさ」に打ち勝つためにも、自社に有利に働き、競争を支配し得るポジショニングを見出すことが「競争戦略」の要諦なのかも知れませんね!
それでは、また!